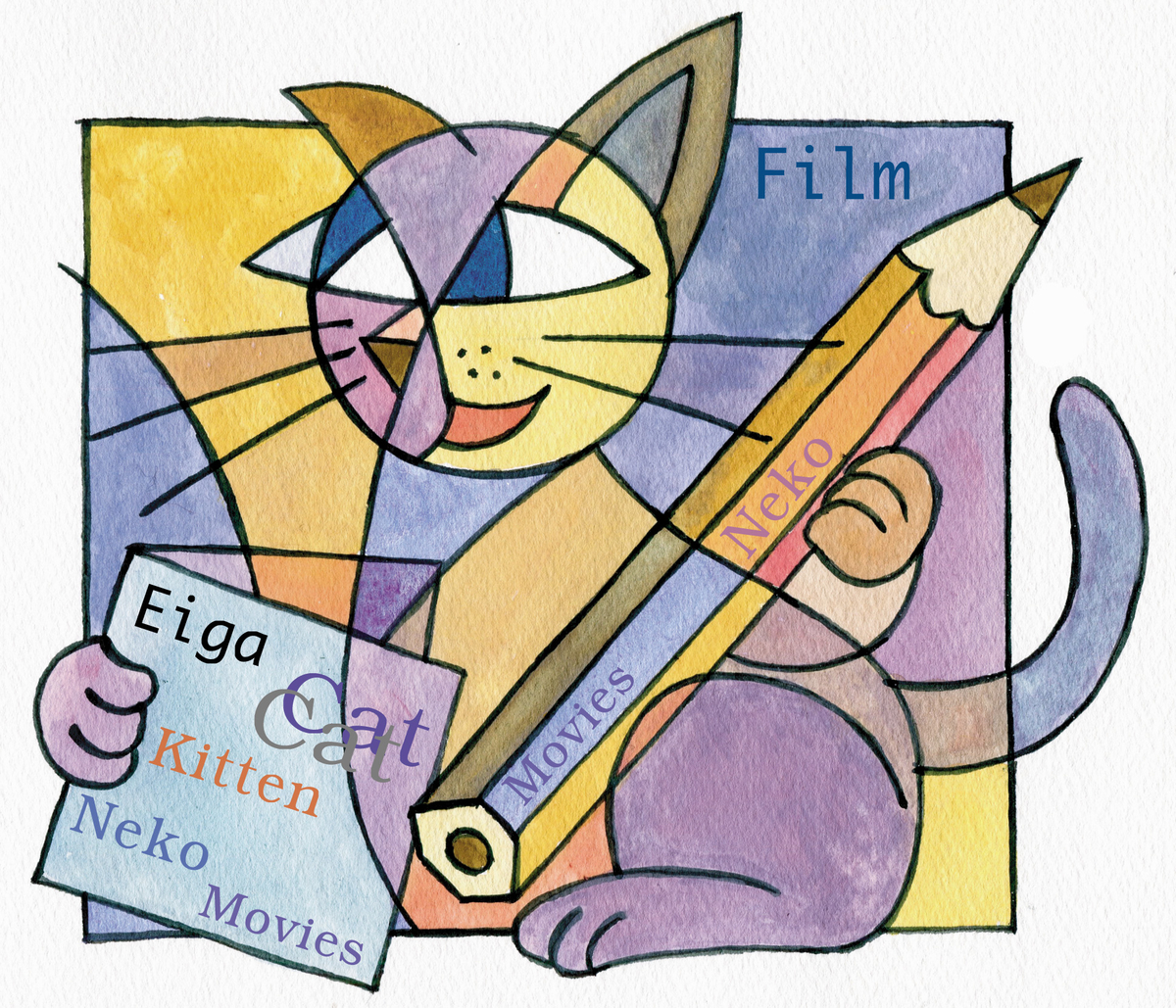吾輩は主人公である。だから、最初から最後までずっと出ている。猫好き諸君には喜んでほしいのだが、猫の扱い方でちょっと目をつぶりたくなる場面がある。日本映画の歴史の一断面として、少し我慢して見てくれたまえ。
製作:1975年
製作国:日本
日本公開:1975年
監督:市川崑
出演:仲代達矢、波乃久里子、伊丹十三、岡本信人 他
レイティング:一般(どの年齢の方でもご覧いただけます)
◆◆ この映画の猫 ◆◆
役:☆☆☆(主役級)
苦沙弥先生の飼い猫
名前:なし
色柄:ロシアンブルー
その他の猫:車屋のクロ、二絃琴の師匠の猫・三毛子
◆日本で一番有名な猫
第1回目の『第三の男』のあとは日本映画をもってこよう、何を選ぼうか、と考えた結果、文豪夏目漱石原作の『吾輩は猫である』を最初に持ってくるのが格としてふさわしいと思い、この映画を選びました。
断っておきますが、この映画、前回の『第三の男』以上に面白くない・・・かもしれません。原作を読んだ方ならご存じのように、この小説は猫の目を通した人間批判。飼い主の先生とその身の回りの出来事を、猫がいささか皮肉っぽくコメントするから面白いのですが、それを映画化した場合、その面白さがどのように生かされているかが一番の見どころだと思います。監督と脚本の腕が試される一作です。
◆あらすじ
明治後期、東京の中学の英語教師・珍野苦沙弥(ちんのくしゃみ)先生(仲代達矢)は、友人の迷亭(伊丹十三)、門下生の寒月(岡本信人)らと、今日も世間話で時間を潰している。苦沙弥先生の家に迷い込んで住み着いた猫は名前も付けてもらっていない。先生の絵のモデルになったり、隣の車屋の乱暴者の猫・クロにすごまれたり、二絃琴の師匠(緑魔子)の美猫・三毛子のもとに通ったり、と猫らしく自由に徘徊して暮らしている。
ヒマで気楽に見える苦沙弥先生だが、神経質で、英語教師が嫌で、胃弱に悩まされている。寒月は、金持ちの実業家の令嬢・金田富子(篠ヒロコ)に見染められ、博士になれたら婿に、という話が持ち上がっている。実業家の金田(三波伸介)は、苦沙弥先生の家の裏の落雲館中学に多額の寄付をしているが、そこから野球のボールが先生の庭に飛び込んでは先生の神経をすり減らすし、先生は金田家の成金臭いふるまいが気に入らない。
金田は寄付金をわいろに大臣の座を手に入れようとしていたのだがかなわず、寒月は故郷で妻をめとり、以前苦沙弥先生の書生だった三平(左とん平)が金田の令嬢と結婚することになった。三平が前祝いにとビールを持って訪れ、苦沙弥先生と友人一同で乾杯する。猫の吾輩は人間がビールで口数が多くなったのを見て、自分も陽気になりたいとコップに残っていたビールを飲んでしまった・・・。

◆「吾輩」の猫たち
日本映画で、ストーリーに猫が絡むものは少ないようです。いまはタレント猫もたくさん登場していますが、この『吾輩は猫である』の頃までは動物プロダクションなどあまりなかったのではないかと思います。『吾輩は猫である』は1936年に山本嘉次郎監督が一度映画化していますが、そちらは見たことがありません。
吾輩を演じた猫は、ロシアンブルーのティムという猫。オス4歳。ちゃんとタイトルにもクレジットされています。明治時代の日本の猫の話なのに洋猫を使うのはしっくりこないと、公開当時思っていました。いま見ても明治のノラ出身の猫とは思えないけれど、なかなか思索的な顔つきを見せ、一言ありそうな感じがするので採用されたのでしょう。原作の吾輩は「波斯(ペルシャ)産の猫の如く黄を含める淡灰色に漆の如き斑入り」とありますが、ちょっと見当のつかない色柄です。猫の図鑑や猫の毛の色を解説した本などにも、これじゃないかと思われるものは見当たりません。本の表紙や挿絵にも、吾輩の決定版の姿は描かれていないようです。夏目漱石先生の筆はありきたりな描写を嫌うあまり、摩訶不思議な猫像を作り出してしまったのかもしれません。
車屋のクロ役の猫はその名も同じく黒。オス12歳。原作の「猫中の大王」という形容通りの見事な貫禄。猫界の安部徹です。吾輩あこがれの三毛子役の猫はメス1歳のミーコ。かわいい。悶絶するほどかわいい。吾輩ならずとも胸がときめきます(猫の名前と年齢はウィキペディア「吾輩は猫である(映画)」より)。
いまは、オスもメスも避妊手術を施されている猫が多いですが、このティム君には、立派なオスのタマタマがついています。それを見てお久しぶりと懐かしく、しばし遠い目になってしまいました。
なお、迷亭役の俳優であり映画監督の伊丹十三は、猫好きで知られていました。
◆猫はなんにも言えないけれど
冒頭でも言いましたが、この映画では、猫に対する乱暴な行為がいくつも見受けられます。日本文学史上最も敬愛されるべき猫の映画だというのに残念です。
苦沙弥先生が吾輩に帽子を投げてぶつける、車屋のクロが、おかずのシャケを取ったとおかみさんに蹴飛ばされる、吾輩が手で払いのけられる、襟首をつかんで放り出される、頭を叩かれる(叩かれたとき小さく声を出す様子が映っている)など。車屋のクロが、宿敵のイタチを捕まえるときに最後っ屁の攻撃に遭っても大丈夫なように、石に何度も自分の鼻をぶつけて潰すシーンはひどい。よく見れば、効果音で激しくぶつかったように見せかけているようですが、ハリボテの石に向かって人間がお寺の鐘の撞木のように猫を押さえて何度も往復させて映したようで、ぶつかりそうになる瞬間にさすがのクロも顔をしかめて嫌がっています。かわいそうで見ていられません。
そして、原作通りビールで酔っぱらった吾輩は水がめに落ちてしまうのですが、本当に猫が水中でもがくさまを映しています。透明の水槽に猫を入れて横から撮影したのだと思いますが、そうまでしておぼれる様子を映像にする必要があったのでしょうか。ティムだったにしろ、スタントの猫だったにしろ、安全に配慮したとは思いますが、一発OKだったのか何度も撮りなおしたのか、などなど、そのときの猫の恐怖を思うと見るに忍びない気持ちです。
◆映画は時代を映す
漱石先生の原作を読むと、かわいがられてはいるのですが、やはり、蹴とばしたり叩いたりのアクションが描写されています。書生だった三平に至っては猫を煮て食べたことがあると言っています。今のようにペットは家族の一員というより、人様とそれ以下の生き物、という一線が存在していたのでしょう。だからこそ、猫が人間社会を一段高いところから批判的な目で見つめる、という逆説的な面白さが小説『吾輩は猫である』のヒットの理由だと思います。
昔の日本映画を見ると、猫の扱い方が乱暴なことが多いのに気づきます。抱いていた猫を下ろすとき、飛び降りやすいようにおろしてやるのではなく放り投げたり、襟首を後ろからつかんで持ち上げたり。襟首をつかむのは、猫キックや爪で引っかかれたり噛まれたりの攻撃を受けないためにはよいようですが、おとなの猫が自分の体重を首の皮で支えて吊り上げられるのはいかにも苦しそうです。
これからもこのブログで取り上げる古い映画に猫を粗末に扱う場面が出てくることがある、ということはお断りしておきます。今とは違う文化だった・・・のです。
◆◆(猫の話だけでいい人はここまで・・・)◆◆

◆誇張された俗悪さ
「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」の有名な書き出しで始まり、全編猫の目で物語られて行く原作小説ですが、映画は猫は猫として擬人化せず、おしまい近くなるまで吾輩のモノローグはありません。つまり、映画では吾輩の目でなく、観客の目が苦沙弥先生とその周囲の人間模様を観察することになります。言ってみれば、どうでもいいことで日々を営んでいる人間の、その滑稽さや哀しさを猫のように一歩離れた目でキャッチできるかどうか、それがこの映画を楽しめるかどうかのキーでしょう。
けれども、アクセントとして挿入された、苦沙弥先生の子どもがご飯をぐちゃぐちゃにしてしまうところや、金田家の令嬢富子が好物の安倍川餅を下品に食べるところとか、落雲館の生徒が野球のボールを苦沙弥先生の庭に飛び込ませて先生をからかうところなど、誇張された演出が戯画的なおかしさに昇華しきれず、不快な部分もあります。インテリで尊敬されるべき苦沙弥先生(漱石自身)のような人間が世間的な成功には縁がなく、金や欲にまみれ道理をわきまえない俗悪で軽蔑すべき人間が幅を利かせている、という夏目漱石が抱いていた怒りや嘆きは見て取れるのですが、映像化の過程で、人間の俗悪さが原作の滑稽さを通り越して、醜さにまでなっているように思います。このオーバーな演出は、猫の扱いと共にやはり減点ポイントでしょう。
ついでに、苦沙弥先生の姪の雪江(島田陽子)のセミヌードや金田が二絃琴の師匠とできているというのも観客サービスのおまけ。原作にはありません。
◆原作を読まずしてこの映画を見ることなかれ
私は、この映画を見る前に、半分くらいまででいいので原作を読んで雰囲気をつかんでおくことをお勧めします。これは人間のどうでもいい日常をやや離れたところから眺めるように作られた映画で、見る側はさらにそれを「眺める」気持ちで見るのが、この映画に合った鑑賞法ではないかと思うのです。先ほども言いましたが、自分自身が猫の目になることが必要なのです。そして、一歩離れた目で人間の営みを分解して見せた市川崑監督の映画に『東京オリンピック』(1965年)があります。記録か芸術かの論争が世間を騒がせました。
市川崑監督は92歳没と長命だったので、その生涯にたくさんの映画やテレビドラマを残していますが、スタイリッシュで、垢ぬけた演出が見られます(たとえば映画『黒い十人の女』(1961年)、テレビ『木枯し紋次郎』(1972年)など)。市川監督は計算された端正で冷静な映像作りが特徴だったように思います。見る側を熱っぽい興奮に落とし込まない。好き嫌いが分かれるかもしれません。
市川崑監督の、一歩遠いところで映画を作っているようなスタイルは、吾輩の目、という気がします。やはり、『吾輩は猫である』を映画化できるのは、この時代、市川監督しかいなかったのではないかと思います。ラストの、苦沙弥先生と奥さん(波乃久里子)の静かなシーンが、私は好きです。