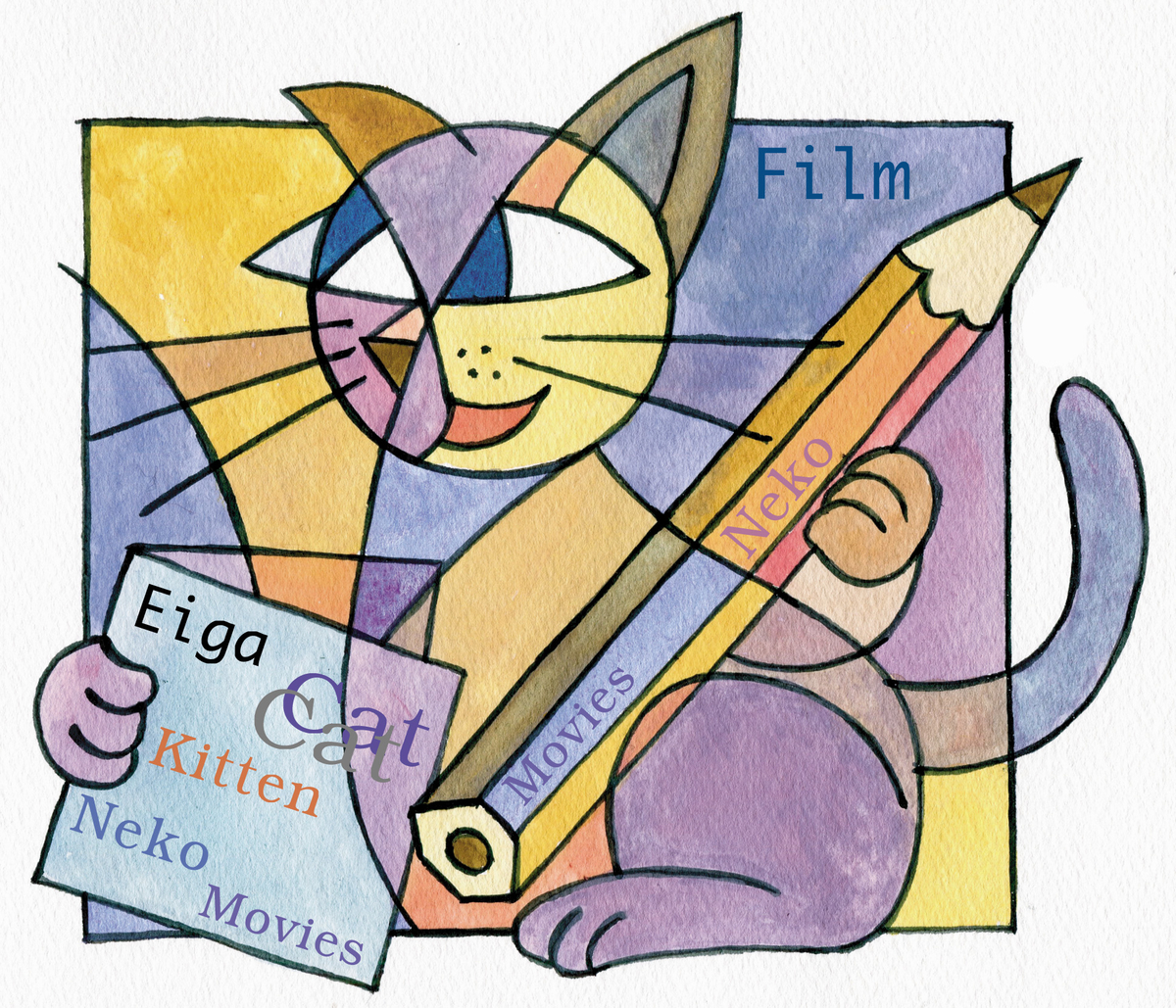盲目の花売り娘に捧げた男の純愛。人の心の美しさをうたうチャップリン不朽の名作。
製作:1931年
製作国:アメリカ
日本公開:1934年
監督:チャールズ・チャップリン
出演:チャールズ・チャップリン、ヴァージニア・チェリル、フローレンス・リー、
ハリー・マイヤース、 他
レイティング:一般
◆◆ この映画の猫 ◆◆
役:☆(ほんのチョイ役)
窓辺の猫
名前:不明
色柄:茶トラ(モノクロのため推定)
◆言葉はいらない
あまりにも有名なこのチャップリンの映画、感動のラストをほとんどの方がご存知と思いますが、知っている気になってしまって実際は見ていないという方も多いのではないでしょうか。かく申す私も長い間その一人でした。今では結末がわかっていてもやはり涙を流してしまう一本となっています。
ストーリー作りに着手してから完成するまで3年以上、その間に映画はサイレントからトーキーの時代へと変化します。この映画がアメリカで公開された1931年には日本でも初のトーキー『マダムと女房』(監督:五所平之助)が製作されていますが、『街の灯』は「A COMEDY ROMANCE IN PANTOMIME」とタイトル部分にわざわざ表記されているところから、この頃にはアメリカではトーキーが主流になっていたのではないでしょうか。役者がセリフを発声することなく、効果音や音楽だけが入った字幕付きのサウンド版という形で作られています。チャップリンも日本の小津安二郎監督もトーキーには否定的で、チャップリンが初のトーキー作品『チャップリンの独裁者』を作ったのはずっと後の1940年です。
ラストの感動に持って行くためには『街の灯』は「トーキーではない」ということが必須だったと言えるでしょう。そのことはまた後ほど。
◆あらすじ
アメリカのとある街にチョビ髭の浮浪者(チャールズ・チャップリン)がいた。
ある日道を渡ろうとした浮浪者は、駐車中の自動車が行く手をふさいでいたので、ドアを開けて中を通り、反対側のドアから降りる。その時、美しい花売り娘(ヴァージニア・チェリル)が声をかける。お金持ちが車から降りたと思ったのだ。浮浪者は一輪の花を買おうとして彼女が盲目だと気づくと、彼女の手にコインを握らせてお釣りを受け取らずに去る。
夜になり、浮浪者は野宿しようと川べりにやって来るが、金持ちの男(ハリー・マイヤース)が身投げを図ろうとするのを見て必死に止める。金持ち男は思いとどまり、浮浪者を親友だと言って豪邸に迎え、愛車をくれるとまで言い出す。
浮浪者は豪邸の前で花売り娘を見かけ、金持ち男の車で娘をアパートに送り届ける。娘は年老いた祖母(フローレンス・リー)と二人暮らしで、浮浪者のことをお金持ちの紳士だと祖母に話し、好意を抱き始める。そんなとき金持ち男がヨーロッパにしばらく滞在することになり、浮浪者は資金源を失ってしまう。
その頃、病気で寝ていた花売り娘宛てに、家主から明朝までに家賃を払えないときは立ち退けという手紙が届く。浮浪者は彼女の部屋を訪れ、手紙に気が付くと明朝までにお金を届けると言って出て行く。
浮浪者は賞金を狙いボクシングの試合に出るがKO負け。そこへ折よく金持ち男が帰国して、事情を話した浮浪者は娘のために千ドルを用立ててもらえる。そのとき金持ち男の屋敷に強盗が忍び込み、浮浪者と金持ち男は強盗を追い払うが、警察が来て大金を持っていた浮浪者は強盗と間違えられてしまう。
追手を逃れ、翌朝娘のところにやってきた浮浪者は、これで家賃と目の手術をと、娘にお金を渡したあと警察に捕まり、牢屋に入れられてしまう・・・。

◆ストライク!
花売り娘のアパートは古いつくり。隣の建物なのか、彼女のアパートなのか、建物の1階の一部のトンネル状の通路を通り抜けると外階段があり、そこを上れば娘の部屋のある2階に入れるようになっています。
金持ち男の車で娘をアパートに送り届けた浮浪者。娘が上る外階段の上には別の部屋の窓があって、そこに茶トラと見える長毛の猫が座っています。部屋に入ろうとする娘の手を取ってうやうやしく口づけをする浮浪者。
「またお送りしてもいいですか」
「いつでもどうぞ」
二人の間には恋が芽生え始めています。
浮浪者が名残惜しそうに彼女が入っていった部屋を見つめていると、茶トラの猫が窓辺の植木鉢を落っことして浮浪者の頭を直撃。それにもめげず浮浪者は彼女の部屋をのぞき込んでいます。
テーブルなどの高いところに猫が乗ったとき、小さな物があるとチョンチョンと手で触って落っことすことがよくあるようです。猫は動かない物に対する視力があまりよくないそうなので、とりあえずさわってそれが何かを確かめているうちに落っことしてしまうのかもしれません。
当ブログのお抱え絵師茜丸の猫は、仏壇に忍び込んでお供えのお茶を飲むそうですが、何一つ倒したり動かしたりしないそうです。猫の仕業と気づく前は、いつの間にかお茶が減っているので不気味だったとか。猫は私たち視覚優位の人間とは全く違う方法で空間を認知し、行動しているのかもしれませんね。
そんな猫なら植木鉢なんかよけて通るのは朝飯前のはずですが、この茶トラは見事に植木鉢を浮浪者の頭上に落としてみせます。
猫が登場するのは開始から31分30秒過ぎ頃です。
◆◆(猫の話だけでいい人はここまで・・・)◆◆

◆花売りの娘
以前にご紹介した『チャップリンの黄金狂時代』(1925年/監督:チャールズ・チャップリン/以下『黄金狂時代』と表記)と比較してドタバタが抑えられ、よりヒューマンドラマ色が濃くなった作品です。爆笑というよりはクスクス笑いと言ったところ。
『黄金狂時代』では主人公の男は金の鉱脈を求めて山に入る探検家。『街の灯』では浮浪者です。1929年の大恐慌後、破産してこの主人公のように野宿する人があちこちで見られたようです。タイトル部分のキャスト表記でチャップリンの役は「a tramp(浮浪者、放浪者)」と明記されています。ちなみに似たような名前のあの方のスペルは「a」ではなく「u」ですのでお間違えなきよう。
この映画でうまいなあと思うのは、花売り娘との出会いです。目の見えない花売り娘が、浮浪者をお金持ちの紳士だと勘違いするために使われるのは自動車。
浮浪者が誰かの車の中を通ってドアを閉める音で、盲目の娘は誰かが車を降りたと思い、ステータスシンボルである自動車を降りた人、すなわちお金持ち、と勝手に思い込みます。浮浪者は娘から差し出された花を仕方なく買おうとしてぶつかり、娘が道路を手探りしながら落とした花を捜しているのを見て、彼女の目が見えないと悟ると、コインを娘の手に握らせます。
そのとき車の主が戻って来て車に乗り込み、ドアをバタンと閉めると、娘は花を買ってくれたお金持ちの紳士にお釣りを渡し損ねたと、車の過ぎ去った方を向いてしまいます。浮浪者はお釣りがほしかったのに、声を掛けたら自分が自動車の主のお金持ちではないとばれてしまうので、そーっとその場を離れます。
この場面をこうして言葉にしましたが、なんとまだるっこしく、くどい説明になってしまうことか。実際の映画には言葉はわずかな字幕以外出てきません。それでいてこの説明以上に、二人の間に生まれる感情を豊かに観客に伝えています。
◆非言語の力
いつもこのブログで「あらすじ」をまとめるたびに、セリフはよほど印象的でない限り忘れてしまっていたり、重要なヒントがちゃんとセリフの中で言われていたことにあとから見返して初めて気づいたりすることが多いと思い知らされます。
表情やしぐさ、声の調子などで、直接的に相手に感情などを伝える言語を介さないコミュニケーションを、非言語コミュニケーション(ノンバーバル・コミュニケーション)と呼びますが、チャップリンや小津安二郎は、そうした言語を介さないコミュニケーションや表現の力を痛感していたからこそ、トーキーに抵抗したのだと思います。特に1910年代から言葉の垣根を越えたスラップスティックの笑いを届けてきたチャップリンにはその思いが強かったのではないでしょうか。
後年、チャップリンの名作『ライムライト』(1952年)では、チャップリンの演じる主人公は、自殺未遂のバレリーナを盛んに言葉で励まします。けれども、その言葉はどこか心の奥底まで響いてこないのです。
◆喜劇を生む体
言葉がいらないといえば、おなじみのドタバタ場面。
花売り娘のために家賃を工面しようと、ボクシングの試合で賞金を狙う浮浪者。手ごわい相手を前にレフェリーを間に挟んでパンチを繰り出したりと、綿密にリハーサルを繰り返し磨き上げたチャップリン得意のフィジカルなギャグが炸裂。
けれども、このときチャップリンも40代。彼の初期の映画の、実際より速く見えるスピードが目に焼き付いているせいかもしれませんが、どことなく動きが鈍いのです。のち次第にヒューマンドラマや社会風刺作品を手掛けていくようになるチャップリン。体を張ったスピーディなギャグがきつくなってきた頃なのかもしれません。
この『街の灯』もノーマルスピードより若干速いのですが、チャップリンは他の出演者に比べると、初期の映画風のカクカクとした動きが際立っています。あの動きはフィルムのコマ数のせいだとばかり思っていましたが、チャップリンに関して言えば、彼がギャグのために磨き体に沁み込ませた芸なのだとハッとしました。偉大なり、喜劇王チャップリン! 彼は体そのものが笑いなのです。
◆沈黙は金
さて、浮浪者は牢屋を出たあと、彼からもらったお金で手術をして目が見えるようになり、花屋を開いた娘と再会します。娘は浮浪者があの親切にしてくれた紳士だと気づかず、ボロ着の彼を憐れんで花とコインを渡そうと声をかけます。
この映画が再びトーキーにはない威力を発揮するのはこのときです。娘に話しかけられた浮浪者はもじもじしながら一言も言葉を発しません。言葉を発したら、娘には声であの紳士だとわかってしまうでしょう。感動のクライマックスが成り立つには、浮浪者が声を発しなくても不自然ではないというシチュエーションが必要です。娘がコインを渡そうと浮浪者の手を取って初めて「You?」と気づくラスト。ここに持って行くにはトーキーでは無理なのです。
このラストのためだけにチャップリンがトーキーではなくサウンド版を選択したのではないかもしれませんが、人間の心のひだを描くには、言葉よりマイムだということを知り尽くしていた彼ならではの選択ではないでしょうか。
◆イマジン
『黄金狂時代』の記事で『チャップリンの独裁者』の演説について言及しましたが、いまだに世界はその訴えるところに近づいていないどころか、不気味な分断がますます広がっているように見えます。人を陥れ、傷つけるのも言葉であれば、チャップリンの演説のように理想を訴え、人を動かすのも言葉です。けれどもそれは諸刃の剣で、悪にもなり善にもなる可能性を秘めています。
1通のメールをもらって、それをどう解釈するかで悩んだ経験は誰にもあると思います。良くも取れれば悪くも取れるのが言葉。そこにその言葉の主の微笑みや怒った顔などの情報が伴えば、誰も悩んだり誤解したりすることはないはずです。いわゆる「炎上」には、こんな要因が絡んでいる場合もあるでしょう。デジタル社会になり、言語外の情報をキャッチする機会を私たちは失いつつあります。
言葉を介さないサイレント映画は、前頭葉ではなくハートに語りかけてきます。私たちは言葉以外のコミュニケーションの力について、あらためて考えるべき時に来ているのかもしれません。
◆関連する過去作品
eigatoneko.com
eigatoneko.com
◆パソコンをご利用の読者の方へ◆
過去の記事の検索には、ブログ画面最下部、オレンジのエリア内の「カテゴリー」「月別アーカイブ」または
検索窓をご利用ください。